奔放な女性ルルへの深い共感 ― 未完の傑作として名高い〝ルル〟は20世紀オペラでも12音技法を駆使した大変な難曲。然しカール・ベームの演奏は少しも難解に聴こえてこない。寧ろリヒャルト・シュトラウスの延長上のような甘美なロマン性に溢れた情感が濃い、その自然さが魅力だ。ベームの20世紀演奏史における比類なき偉業の一つにベルクの作品普及への貢献が挙げられる事は間違いあるまい。特に『ヴォツェック』と『ルル』の2つの歌劇は偉大なる先達エーリッヒ・クライバーが働き盛りで急逝した事もあり、ベームが絶対的権威として世界にその存在感を誇っていた。これに対し、鬼才の管弦楽作品に関してはそう積極的に採り上げたとは言えない様だが、しかしベームの演奏するベルクが他の追随を許さぬものを持っていた事は確かであろう。〝ルル〟は未亡人ヘレーネがベルクの師シェーンベルク以外の補筆を禁じ、完成していた2幕までと「ルル組曲」の抜粋という形で初演されたが、後半に書いているので先にそちらを読んでから、ここに戻ってきてもらうと話がスムーズだ。20世紀前半の音楽史に重要な功績を残した新ウィーン楽派の作曲家たちのなかで、アルバン・ベルクはある意味で特異な存在だったと言えるだろう。後期ロマン派から無調へ、さらに12音技法の創始者として、時代を切り開いていった師シェーンベルク。師の世界をさらに推し進め、前衛の時代の絶対的な規範となった盟友ウェーベルン。しかしながら彼らの道のりは同時に、20世紀の音楽が抱えることになった問題、すなわち聴衆との断絶を広げるものだった。そのなかでベルクはオペラ《ヴォツェック》によって興行的な成功を手に入れ、ストラヴィンスキーの《春の祭典》が20世紀音楽の古典と呼ばれるのと同じく、ベルクの《ヴォツェック》は1925年のベルリン初演以来、20世紀オペラの古典と評される。「歌う声による伴奏付き大オーケストラのための交響曲」となってしまった楽劇から、オペラを「退屈な劇」とすることなく、「人間の声に仕える芸術形式」へと取り戻すこと。そこにはオペラ作曲家としてのベルクの信念があった。そのために2作目のオペラである《ルル》にも、より拡大されて受け継がれている。ベームは20世紀半ばから後半のドイツ・オーストリア音楽界にこの人あり、と謳われた名匠です。1917年に指揮者デビューしたが、その頃はグラーツ大学で法律を専攻し、1919年に博士号もとっている。1921年からバイエルン国立歌劇場の指揮者として研鑽を積み、ダルムシュタット歌劇場、ハンブルク国立歌劇場の音楽監督を歴任。1933年にはウィーン国立歌劇場でウィーン・フィルハーモニー管弦楽団を指揮してデビュー。1934年にはドレスデン国立歌劇場の音楽監督に就任。ベームが世界的に名声を得るようになったのは第2次世界大戦後の、LPレコード時代になってからのこと。ウィーンを中心に活動し、欧米各地で客演。1954年にウィーン国立歌劇場に復帰したが国外活動が多いとの批判を浴び2年間で辞任。それ以降は特定のポジションに就かず、世界の主要な音楽祭やオーケストラ、歌劇場で活躍した。主要なレパートリーはブルーノ・ワルターの薫陶を受けたモーツァルトやワーグナー、作曲者と親交があったベルクやリヒャルト・シュトラウスなど、独墺ものを得意とし名盤も数多い。バイエルン国立歌劇場では音楽監督だったワルターから、モーツァルト演奏についての多大な影響を受けたとされる。細部をおろそかにしない、地に足のついた演奏でありながら独特の推進力がある。ベームならではの質実剛健なアプローチが作品本来の味わいをよく引き出しています。
関連記事とスポンサーリンク
カール・ベームは1931年にダルムシュタットで『ヴォツェック』を採り上げて以来、アルバン・ベルクと親しく成った。鬼才が急逝した後も、『ヴォツェック』や『ルル』を世界各地で指揮し、作品普及に巨大な功績を残した。未亡人のヘレネとも終生友情で結ばれていた。ベームの生前は、世界の音楽ファンの多くがベームとベルクの関係をよく知っており、絶対的権威とも目されていた。当然、ドイツ・グラモフォンから発売された『ヴォツェック』と『ルル』も決定盤として高い評価を得ていた。共に複数の録音が存在する事も、当時の評判の高さの証だ。ベルクの最大の貢献は、無調の手法を使って大規模な作品を作り上げることが可能であることを現実に証明した事です。このオペラのプロローグで猛獣使いが登場します。そして、彼はルルを「かわいい蛇」として紹介します。これが意味することは、「アダムとイブ」が刷り込まれている西欧人にとっては自明のことなのでしょう。ルルのことを「性欲という原初的な絶対者」とか「地の霊によって人間に禍をもたらすために使わされた誘惑の蛇」と説明される所以です。ルルは世間のモラルなどというものは一切気にすることなく己の本能のままに生きます。そんな奔放なルルには天性の媚態と破壊的な魔性が備わっていて、その魅力に男どもは次々と魅入られて己が身を破滅させていきます。それにしても、この「かわいい蛇」の生き方は凄まじいです。このオペラを見れば、どんな昼メロだってただの子供の遊びに見えてしまうはずです。
《ヴォツェック》が内縁の妻の浮気に怒り、殺してしまう男を描いたのに対し、《ルル》は次々と男性遍歴を重ねた挙句、「切り裂きジャック」に殺される女性の波瀾の生涯を描いている。1922年に完成させた歌劇《ヴォツェック》がエーリヒ・クライバーの指揮により1925年に初演され、音楽界に一大センセーションを巻き起こした鬼才アルバン・ベルクは、1928年に歌劇第2作《ルル》に着手する。前作と同様にベルクは自らの手で、フランク・ヴェーデキント(1864~1918)の2つの戯曲、『地霊』と『パンドラの箱』を3幕の台本へと編纂した。それにより《ルル》のドラマは、第2幕の真ん中を頂点に、世紀転換期を生きたファム・ファタル ― フランス語で「運命の女」、すなわち男性を破滅させる魔性の女であるルルが人生を登り詰め、そして凋落していくという、シンメトリー構造のなかに置かれることになった。このルルを中心とする因果応報の世界を、ベルクは12音技法によるオペラとして作曲した。ここでは唯一のルルの音列から、すべての登場人物の音列が導き出され、《ヴォツェック》では場ごとであった器楽形式は、シェーン博士にはソナタ形式、その息子のアルヴァにはロンド形式と、登場人物ごとに与えられている。さらに《ルル》における声は、全くの演劇的な語りからシュプレヒシュティンメ、そして歌にいたるまで、6つのレベルを自在に行き来する。《ヴォツェック》に続く《ルル》で、ベルクはさらなる飛翔を遂げるはずだった。台本完成後、作曲はこつこつと進められ、1934年には第2幕迄完成に漕ぎ着けたが、第3幕に着手した1935年、可愛がっていたマノン・グロピウス(アルマ・マーラーとワルター・グロピウスの娘)が19歳の若さで夭折。その死を悼しんで急遽《ヴァイオリン協奏曲(ある天使の思い出のために)》を手掛けた為、《ルル》は中断。ベルクの《ヴァイオリン協奏曲》は、親しかった少女の死を悼んだレクイエムであると同時に、自らの死を予感した自伝的作品とも言われる。《ヴァイオリン協奏曲》は何とか完成させたものの、虫刺されを原因とする敗血症で、一代の鬼才、ベルクは1935年12月に世を去ってしまう。かくして《ルル》は未完のまま遺された。未亡人と成ったヘレネはベルクの師シェーンベルク以外の補筆を認めなかった為、《ルル》は2幕物として上演される様に成った。尚、ベルクは1934年に新作オペラの宣伝のための『〝ルル〟からの交響的小品(ルル組曲)』を完成させており、これに3幕の音楽 ― 第4曲「変奏曲」と第5曲「アダージョ・ソステヌート(終景)」が含まれていた事から、第2幕に続けて第3幕の2曲を演奏するというスタイルが2幕版上演の定番と成った。ベームもこれに拠っている。すなわち《ルル》は、第3幕の始めまでしかオーケストレーションされなかったが、この方法でも一応「変奏曲」が場面転換の役割を果たし、「終景」がエピローグ的役割を果たしているので、途中が抜けているとはいえ、物語としては完結しているので、未完のまま終わっているという印象が和らいでいるという事も救いだ。
カール・ベームとベルリン・ドイツ・オペラとのスタジオ録音であるが、やはりベルクはウィーン・フィルハーモニー管弦楽団の演奏で聴きたい。ベームはウィーンの南部に位置するグラーツの出身ですから、オーストリア芸術の振興の為には、ウィーン・フィル&シュターツオーパーだけでなく、ウィーン交響楽団等々周辺にも大きく貢献するのは当然という献身的なスタンスを取っていたと言う。本盤の《ルル》もウィーン交響楽団と製作されたDVDがある。モノクロ映像だが、それがシュールな世界観とよくマッチしている。これは20世紀演奏史上に残る記念碑の一つとして、後世に語り継ぐべき価値のある演奏であり映像である。流線型のヘルベルト・フォン・カラヤンや全身全霊のヴィルヘルム・フルトヴェングラーとは違う、なにか古き良きドイツ=オーストリアの雰囲気を感じられるベームの指揮。フルトヴェングラーは時の経過につれて奥深さを痛切に感じるのは聴き手として、わたしが歳を重ねたことにあるのか。今となってはベームの音楽がわからなくなっている。カラヤンを際立てるために同時代にあったのだろうか。膨大なレパートリーの印象がカラヤンにはあるが、1945年以後の音楽には関心がないと明言している。ベームのレパートリーはどうだっただろう。『現在ドイツ、オーストリアに在住する指揮者としては、フルトヴェングラー亡きあと最高のものであろう。』とカラヤンとの人気争奪戦前夜の評判だ。『その表現は的確で、強固なリズム感の上に音楽が構成されている。メロディを歌わせることもうまいが甘美に流れない。彼は人を驚かすような表現をとることは絶対にないが、曲の構成をしっかり打ち出し、それに優雅な美しさを加え、重厚で堂々たる印象をあたえる。まったくドイツ音楽の中道を行く表現で、最も信頼するにたる。レパートリーはあまり広くはないが、彼自身最も敬愛しているモーツァルトや生前親交のあったリヒャルト・シュトラウスの作品はきわめて優れている。しかしブラームス、ベートーヴェンなども最高の名演である。』これが1960年代、70年代の日本でのカラヤンか、ベームかの根っこになった批評ではないか。
Dietrich Fischer-Dieskau, Donald Grobe, Evelyn Lear, Patricia Johnson. Producer – Dr. Hans Hirsch, Recording Supervisor – Wolfgang Lohse, Engineer – Günter Hermanns. Mitschnitt der Neuinszenierung der Deutschen Oper Berlin 1968, Live recording at the Deutsche Oper, Berlin, of the new 1968 production.
YIGZYCN


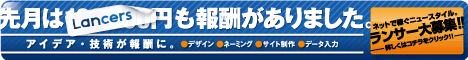

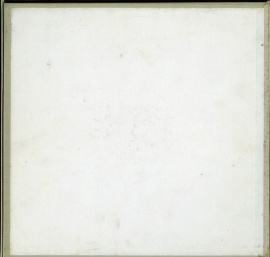
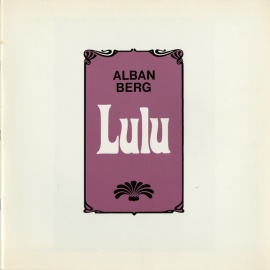
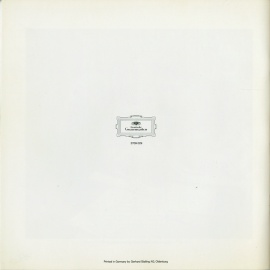









コメント
このブログにコメントするにはログインが必要です。
さんログアウト
この記事には許可ユーザしかコメントができません。